あっという間に2月が終わりました。
2月は逃げると言いますが、まさに逃げていったかのよう。ついこの間新年を迎えた気がするのに。
そんな中で新しく取り組み始めた曲も2ヶ月目に突入しました。
練習を始めるまで知らなかった曲と出会えたことに、改めて感動と喜びを感じた一カ月でした。
弾けば弾くほど好きになる

2月は合計21時間
2月は、12日で21時間練習。
1月と全く同じ時間数になりました。
すっかり日常にピアノの練習が組み込まれて、安定して練習時間を確保できるようになったということだと思っています。
レッスンは2度、合計2時間の先生の元へ行きました。
弾けば弾くほど曲が好きになるゾーンに突入!
年明けから取り組んでいる曲は、シューベルトの「即興曲 ハ短調Op90の1」。
1月はひたすらよちよち歩き、必死に楽譜を追う練習ばかりでしたが、
そんな地道な練習がちょっとずつ実を結び、
どんどんメロディーが耳に入ってくる。
どんどん曲らしくなってくる。
どんどん曲の全体像が見えてくる。
「こんなん絶対に一生弾かれへんわ!」と思っていた超絶難しい部分も、
えらいもので少しずつ慣れて、手応えが感じられるようになってきました。
そして、「こう弾けばしっくりくる」を発見できたシーンが徐々に出てきて、
ただ楽譜を追って弾いていた頃に比べ、「腑に落ちて弾ける」という感覚が増えてきました。
この曲を弾けるようになるのが楽しくてしょうがない!即興曲大好き!というゾーンに突入していきました。
「打鍵」と「ペダル」

ピアノ演奏の基本の基本である「打鍵」と「ペダル」、改めてこの二点の壁にぶつかりました。
レッスン時、先生に、「メロディー部分の音がツブ立ち過ぎている」と指摘されました。
心当たりはありました。
例えば右手がメロディーを弾いているとき、左手は割と難しい伴奏をしていることが多くて、
どうしても意識は左手に行きがちに。
そんな中でもメロディーは目立たせなきゃと思うので、
「左手に気を取られている耳にも入るように、目立たせて右手のメロディーを弾く」というクセがついていたのでした。
メロディー感もフレーズ感もあったもんじゃなく、ただ聞こえるように弾くだけ。
ペダリングも、ただただ何も考えず、何となくペダルを踏んでいる自分に気が付きました。
普通にペダルを踏みかえているつもりが、音がとても濁ってしまっている部分があったのです。
- しっかり踏みかえる部分
- あえて浅く細かく踏みかえる部分
- 伸ばしたい音を弾いてからペダルを踏む
- 音と同時に踏む
など、必要なペダルの技術も違うんだと改めて考えさせられました。
ただメロディーを弾けばいいってもんじゃない。
ただペダルを踏めばいいってもんじゃない。
そんな当たり前のことの奥深さを学び、ちょっとでも理想に近づけるように練習を続けています。
心が不調の時の練習

2月の前半、仕事とプライベートの両方で、心配事や憤ること、気になることなどがとにかく重なり、
精神的にかなり落ち込んでいた時期がありました。
そんな状況でのピアノ練習の、はかどらなさったら。
全く心が乗らなくて、ひたすらミスタッチばかり。
むしろミスタッチをする練習をしているかのよう。
ピアノを弾いていても、頭の中ではぐるぐると違うことを考えたり。
曲のうわべだけをさらーっとなぞっているような感覚で、全然身が入りませんでした。
きっとそういう時は、きっぱりと練習を切り上げた方が良いんだろうな、とは思ったのですが、
せっかく外出したし(私はピアノ練習のため、自宅から、ピアノがある近所の実家に通っています)、
レッスンの日は近づいてくるし、
貴重な練習時間を無駄にするのもなんか悔しいと思い、
開き直って、ひたすら指の運指の練習、苦手なところの部分練習に徹しました。
私の中で筋トレと呼んでいる練習です。
「ピアノを弾いていると嫌なことも忘れる!」というくらい熱中できれば良いのですが、
そうもいかないこともあります。
ただ、落ち込んでいる時でも、「ちゃんと自分で決めた練習日に、ちゃんとピアノを練習している」という事実が、
少しだけ自己肯定感を上げてくれて、少しだけ心が上向きになることができました。
そして不調が明けてからの練習では、
「心が明るくなると、こんなにもスムーズに弾けるもの!?」
と衝撃を受けました。
これは気持ちの問題なのか、不調時の筋トレが身を結んだのかはわかりませんが、
改めて、ピアノって内面がそのまま出るんだなぁと感じた出来事でした。
生きている間に、どれだけの曲を弾けるか?

毎月購読している、月刊ピアノ2月号の、「ピアノ川柳」という読者投稿のコーナーにて。
「ピアノ本 一生勉強 終わらない」
月刊ピアノ2月号/「ドレミファソ・ラボ」より
という投稿がありました。
この川柳を送ったのは、北海道のピアノ講師の方で、
(ピアノの先生をもってしても「一生勉強終わらない」なのか……
いや、先生だからこそそう思うのか……)
としみじみと読んでいると、そのすぐ下に載っていたコメント。
生きている間にどれだけ弾けるか楽しみです。
投稿者のコメントなのか、編集部の方のコメントなのかわからないのですが、
この言葉が心に突き刺さりました。
さらに、ちょうど今現在読み進めている、稲垣えみ子さんの「老後とピアノ」という本にも、同じようなことが書かれていました。
1曲なんとか弾けるようになるには最低3ヶ月かかる。となれば年間4曲ですよ。
となれば死ぬまでに弾ける曲の数は悲しいほど限られている。
「老後とピアノ」稲垣えみ子/㈱ポプラ社
ピアノは老後までの長い趣味にしていくつもりなので、
この先長い時間の中で、無限にいろんな曲を弾けるとぼんやりと思っていました。
そうか……。生きているうちに、ピアノが弾けるうちに、自分が出会えて弾けるようになる曲って、
ほんの少しなんだなぁ。
ちゃんと認識することができたこの事実。
そして、これまでに巡りあってきた一曲一曲が、すごく尊いものに感じられました。
今、シューベルトの「即興曲」と出会えてよかった
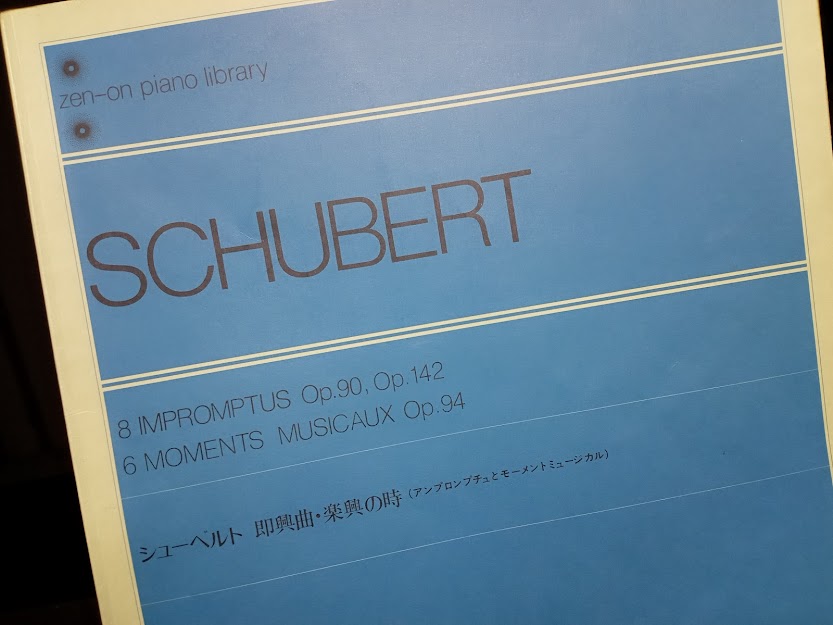
そう考えると、今練習を続けている「即興曲」が、ますます愛しく思えてきます。
実は練習を始めるまで知らなかったこの曲。
有名な「即興曲の二番」は昔に弾いたことがあったので、
(シューベルトの曲って全然知らないし、じゃあ一番をやってみようかな?)
という半ばノリのような理由で決めました。
そして練習を重ねるにつれて、この曲の魅力にどっぷりとハマっています。
どのピアニストの演奏を聞いても、弾き方が全く違う、その自由さと奥深さ。
ドエライ曲を選んでしまった―と思った時期もありましたが、
今、私の今の年齢で、ピアノを再開してピアノを改めて好きになっている今現在、この曲と出会えたことが不思議で、本当に幸せなことだと感じています。
まだまだ弾きこなすには課題だらけ、難しいところだらけのこの曲ですが、
出会えたこの縁を大切に思いながら、引き続き練習を続けていこうと思っています。
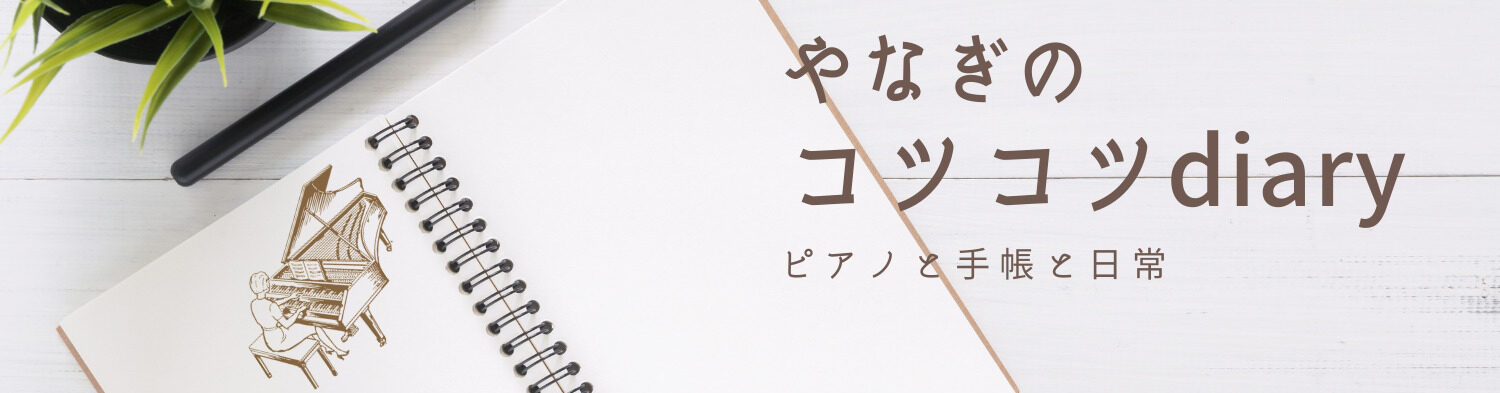



コメント